カウンセリング紹介
当オフィスでは3つの内容でカウンセリングを提供しています。

一般カウンセリング
不安で辛い…
人間関係に困ている…
一人で問題に取り組むとどのように対処してよいか分からないですよね。
一緒に考え、気持ちを楽にする方法を探しましょう。
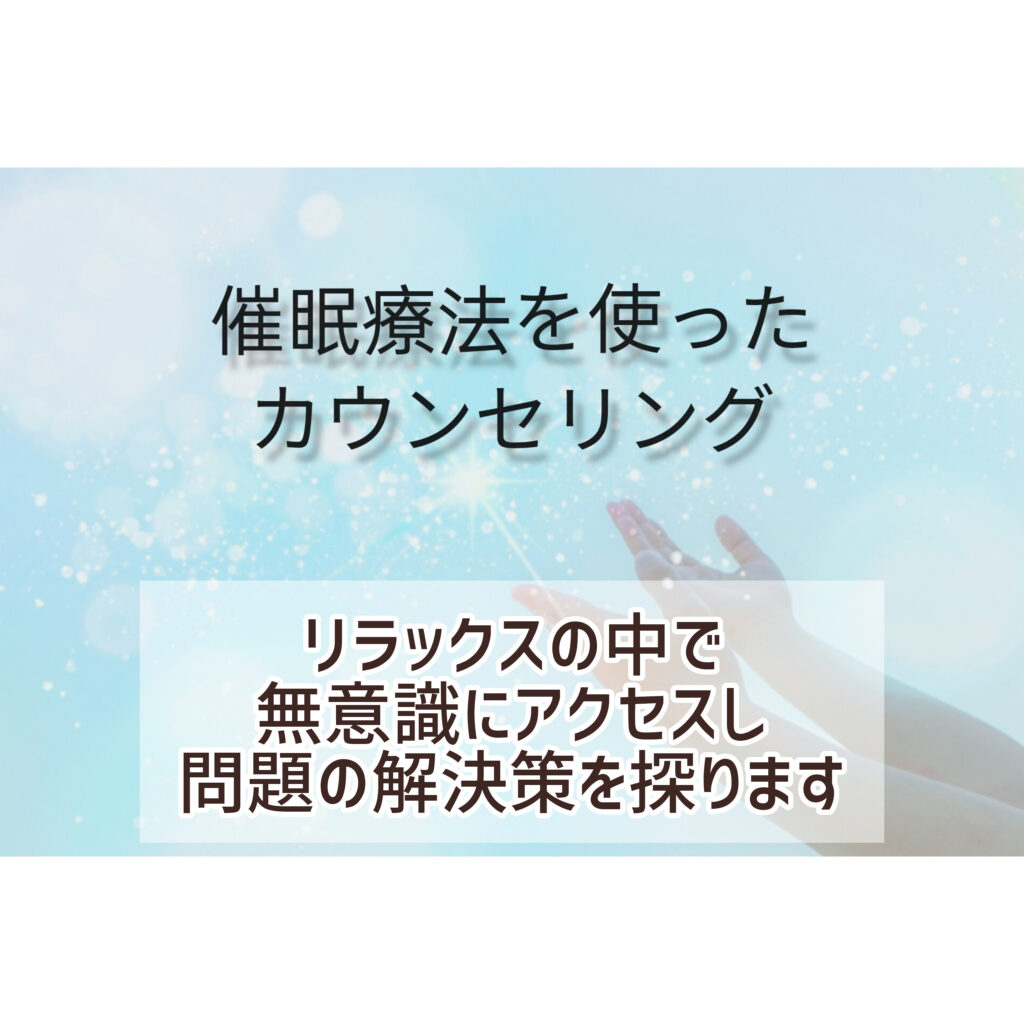
無意識を活用したカウンセリング
自信がない…
行動できない…
このようなお悩みには、無意識を活用したカウンセリングがおすすめです。
催眠というとなんだか怪しいと思う方もいるかもしれません。
実際にはリラックスした状態で、イメージを活用しながら進めていくので、普通に話すカウンセリングよりも緊張せずに話せる場合が多いです。
問題に対して整理したり、解決策を探したり
自分の中にあるヒントを手掛かりに、進めていきます。
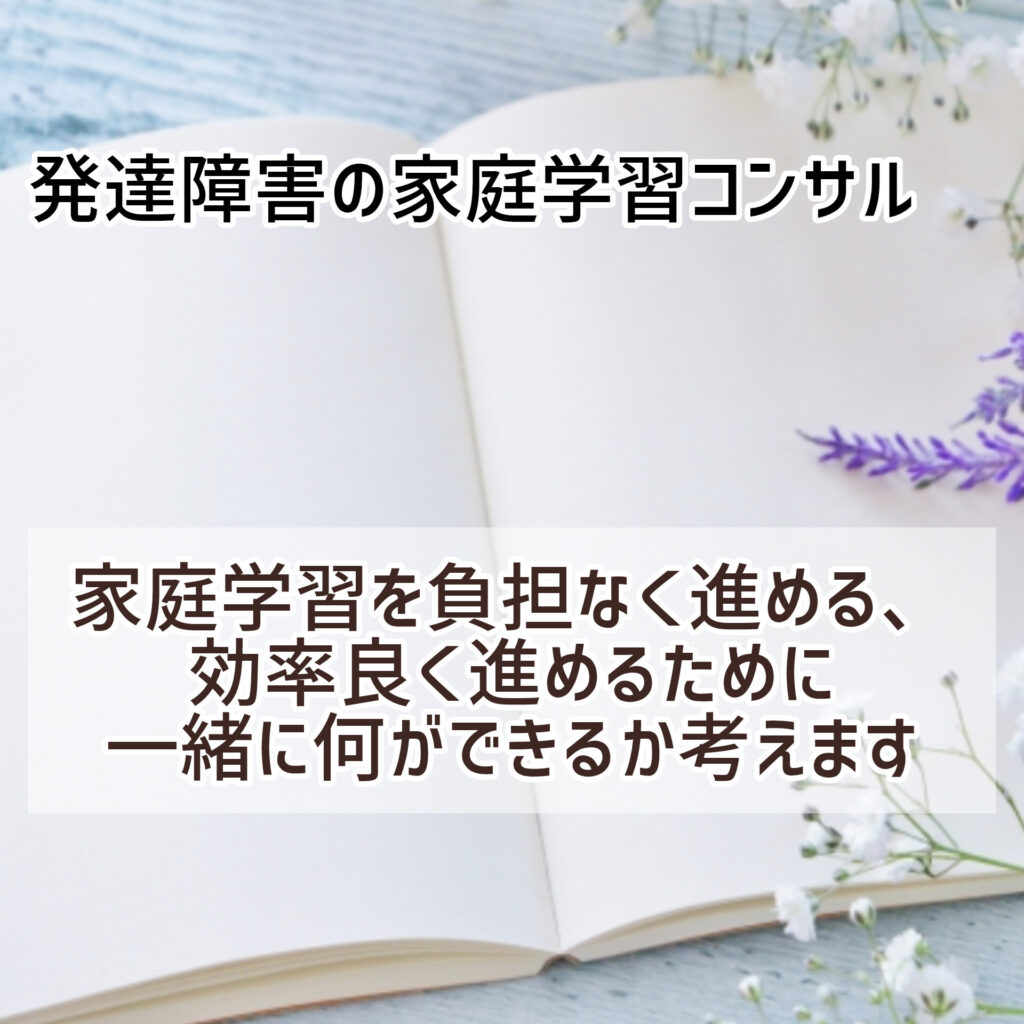
発達障害のお子様の家庭学習コンサルテーション
発達障害のあるお子様は、家庭学習に困る方もいらっしゃいます。
学校の方針と、お子様のペースが合わないこともありますよね。
お子様の様子、得意なこと、癖や特性などを手掛かりに
どのようなアプローチが有効か、
親も子供も楽に学習ができる方法を一緒に考えます。
ご予約について
カウンセリングはオンラインカウンセリング会社のcotreeにて提供しております。
解決方法を探している以外にも、どのような状態か知りたい、ただ話を聞いてほしいなど、ご相談の内容は様々です。
気軽にご相談ください。
